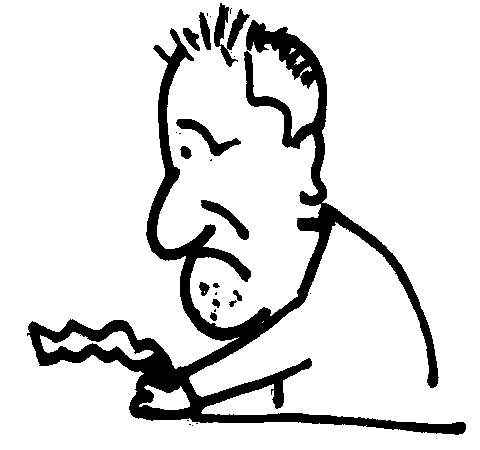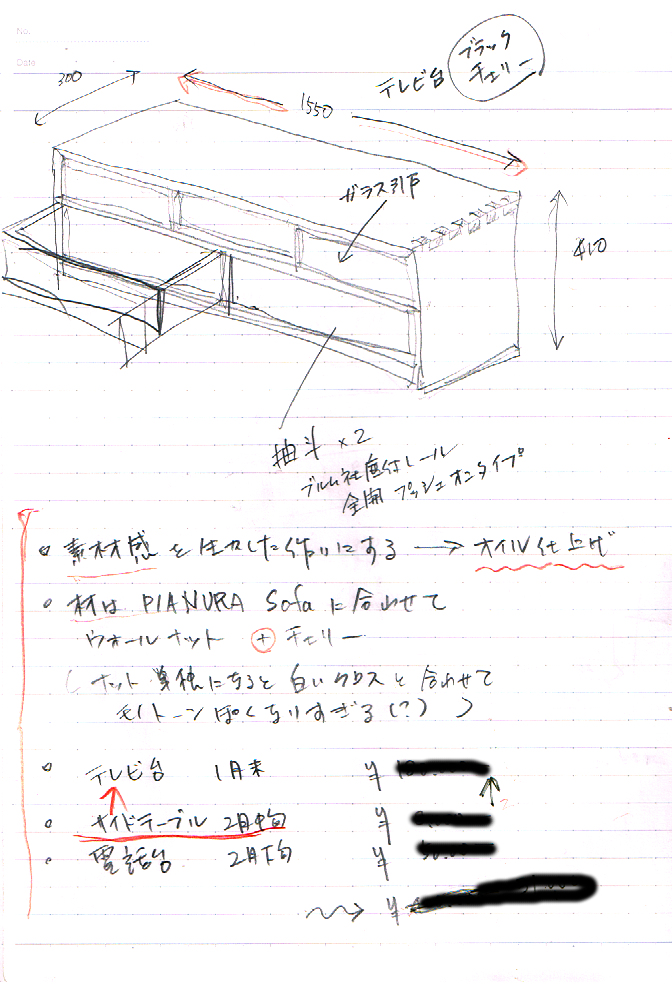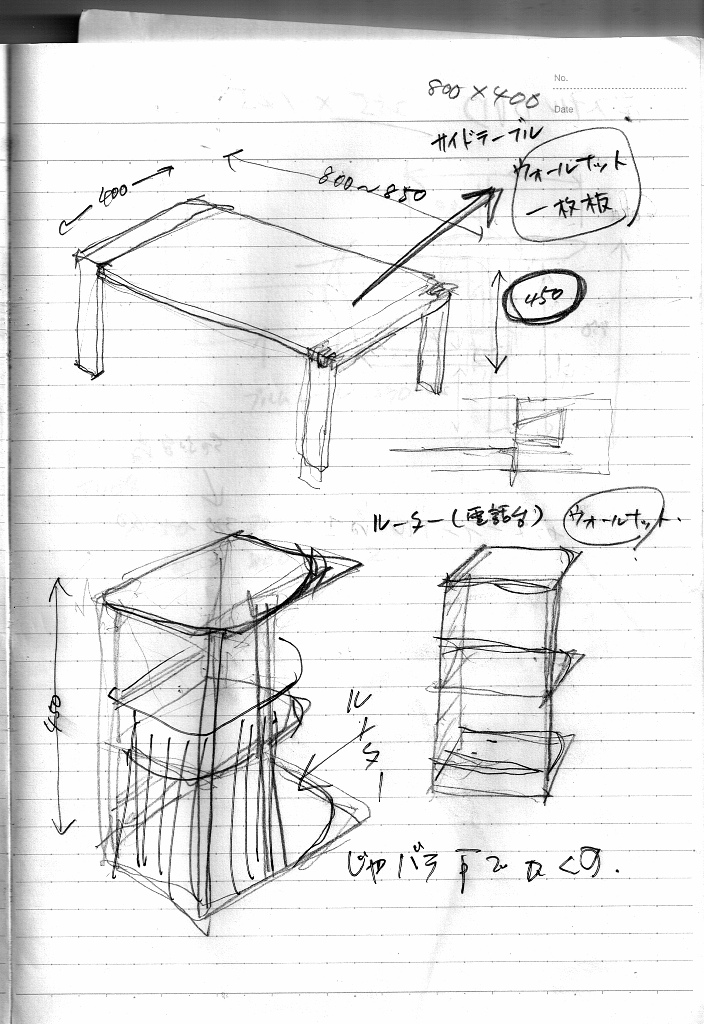先週の展示会が終わり、少し疲れが残っていて、今週初めの雪など不規則な天候で風邪をひいてしまいました。それにいよいよ花粉症がひどくなり、確定申告もあって今週はへたり気味です。そんな中で、今日は(←アップの段階では昨日になってしまいました)岸和田に行ってきました。私の苗字と同じ材木屋さんの製材の勉強会と市があったからです。勉強会の方は、まあどうでも良かったのですが、去年買って、そのまま預かってもらっているクリを、いい加減引き取らなくてはなりません。それと、来年早々に始まる店舗の仕事で、あるまとまった量の什器の材料をそろそろ決めなくてはなりません。
去年買ったクリはいい材でした。買っておいて良かったです。1本の丸太から、400上(幅・400ミリ以上)の板目の板が2枚、300上が3枚、あとは柾目で挽いてあります。しかもすべて耳断ちです。これなら、幅広の板目を中心にして外側に柾目材を接いで、長さ1800・幅800〜900程度の上品な天板が最低でも4枚は取れそうです。これまで、10余年購入してきたクリ材は、すべてダラ挽きと呼ばれる丸太を端から板目で挽いたものでした。しかも最近は通直な材は少なく1800程度の幅の材を取ろうとすると、寸検値の半分程度しか取れません。岩手とか青森からのクリは、そうしたものだとなかば諦めていましたが、そうではなかったのかなと今さら思います。単価は、これまで買ってきたもののちょうど倍ほどしますが、歩留まりとか木取りの手間を考えると納得、というかお得感すらあります。以前のように数をこなしてナンボのような仕事は出来なくなってきた、というかもうやめようと思っているので、材料もより慎重に良い物を選ばねばと思います。
さて、岸和田から寄り道もせず、直で戻ってそのまま材木(クリに加えて小口売りのあったアルダーを少し買った)を降ろしました。その頃には鼻水が止まらず、くしゃみ3連発状態でした。まだ日もあったのですが、かわいそうだけどタローの夕方の散歩をパスして、卵酒に湯豆腐と小女子に大根をおろしたものをサッと食らって床につきました。おかげで変な時間に目が覚めてしまいましたが、体は随分楽になりました。学生時代に寮母さんに作ってもらって以来、インフルエンザなど深刻なものでない限り、私には風邪には卵酒を飲んで早々と床につくのが効果があるようです。