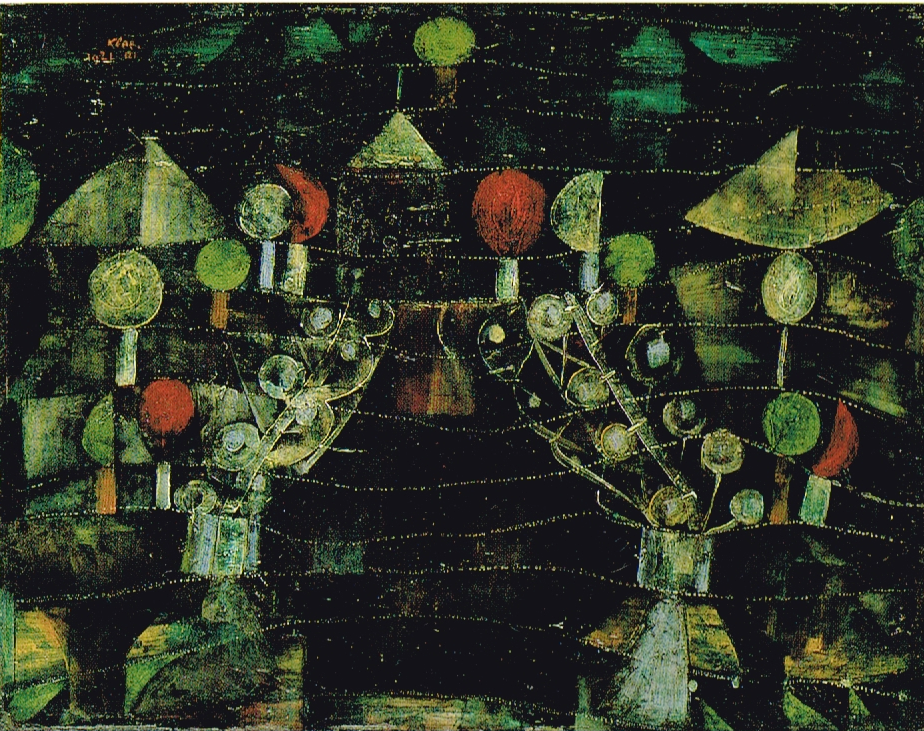暦の上で年が明けたからといって、あらたまって事をいたすなど久しくしなくなった。それでも新年にまず何を読むかは少しは気にする。かと言ってたとえば昨年の正月に何を読んだと記憶しているわけではない。ただあらたまった気分の中、ネットを開いて汚い言葉やひどい日本語だけは目にしたくないと思っている。
今年は内田百閒(機種依存文字。門構えに月)の『ノラや』(内田百閒集成9・ちくま文庫)にした。昨年末のペットロス状態から百閒翁の猫ロスで取り乱した様を読んだら、少しは慰みになるかとも考えた。冒頭に置かれた「猫」という短編から圧倒される。化け猫
という言葉に象徴される猫にまつわる妖気とか禍々しさを、その猫自体の描写を一切なさずに著している。逆にそのことによってこの猫の妖気とそこから「私」にまとわりつくような恐怖と悪寒が滲み出される。後で引用する三島由紀夫の言う究極の正確さをただニュアンスのみで暗示し
、鬼気の表現に卓越している
世界がここにもある。
内田百閒の文章は、三島によれば少しも難しい観念的な言葉遣いなどしていない
、こう書けばこう受けるとわかっている表現をすべて捨てて、いささかの甘さも自己陶酔も許容せず、しかもこれしかないという、究極の正確さをただニュアンスのみで暗示している
。そうした言葉の洗練の極
のゆえか、百閒の文章は3次元的なまたそれに時間もふくめた4次元的なイメージを沸々と呼び覚ます。それは、鈴木清順や黒澤明といった映像美にとりわけ強いこだわりをもった映画監督が百閒の作品の映像化を試みていることからもわかる気がする。私もある事件(一生引きずるであろう忘れてはいけないもの)のあとそれにまつわる夢をなんども見た。それが、百閒のある作品(「冥途」)の中に再現されているように思われて恐ろしかった。今は、その夢と百閒の作品が渾然となってその境がわからなくなったと思うことがある。
同じ漱石の弟子に中勘助がいる。彼の『銀の匙』は学生時代に遠距離
をしていたかつての同級生に送ってもらって読んだ。しかし彼の作品で面白いのはこれだけで(その1編が本当にすばらしいのだが)、あとは自分の兄が嫌いで一方その兄嫁にほとんど恋愛感情な好意を抱いているといった内容の私生活暴露な「小説」ばかりだった。百閒の作品はどれも素敵に面白い。すくなくとも私の持っているちくま文庫の「内田百閒集成」12巻の中にハズレというか駄作はない。これは本当に驚くべきことなのだ。
百閒の文章を手本にしていると言えばあまりにおこがましい。ただ彼の文章を何編か読めば、その虜になるでしょう。それほど魅力的でやはり日本語の文章表現の手本であると思う。そのことは同じく稀有の美文家であった三島由紀夫の百閒に対する絶賛をこめた分析がすばらしく的確で、これまた感心させられる。もっとも三島という人は先達はもちろん同時代の作家に対してもいつも好意的な批評を行っていて、ずいぶん気遣いの細やかな人だったのだと思う。
<内田百閒>解説
三島由紀夫
現代随一の文章家
もし現代、文章というものが生きているとしたら、ほんの数人の作家にそれを見るだけだが、随一の文章家ということになれば、内田百閒氏を挙げなければならない。たとえば「磯辺の松」一遍を読んでみても、洗練の極、ニュアンスの極、しかも少しも繊弱なところのない、墨痕あざやかな文章というもののお手本に触れることができよう。これについてはあとに述べるが、アーサー・シモンズは、
文学でもっとも容易な技術は、読者に涙を流させるとことと、猥褻感を起こさせることであると言っている。この言葉と、佐藤春夫氏の文学の極意は怪談であるという説を照合すると、百閒の文学の品質がどういうものかわかってくる。すなわち、百閒文学は、人に涙を流させず、猥褻感を起こさせず、しかも人生の最奥の真実を暗示し、一方、鬼気の表現に卓越している。このことは、当代切ってのこの反骨の文学者が、文学の易しい道を悉く排して難事を求め、しかもそれに成功した、ということを意味している。百閒の文章の奥深く分け入って見れば、氏が少しも難しい観念的な言葉遣いなどをしていないのに、大へんな気むずかしさで言葉をえらび、こう書けばこう受けるとわかっている表現をすべて捨てて、いささかの甘さも自己陶酔も許容せず、しかもこれしかないという、究極の正確さをただニュアンスのみで暗示している。(中略)それは細部にすべてがかかっていて、しかも全体のカッキリした強さを失わない、当代稀な純粋作品である。後略
『サラサーテの盤』内田百閒集成4 ちくま文庫所収